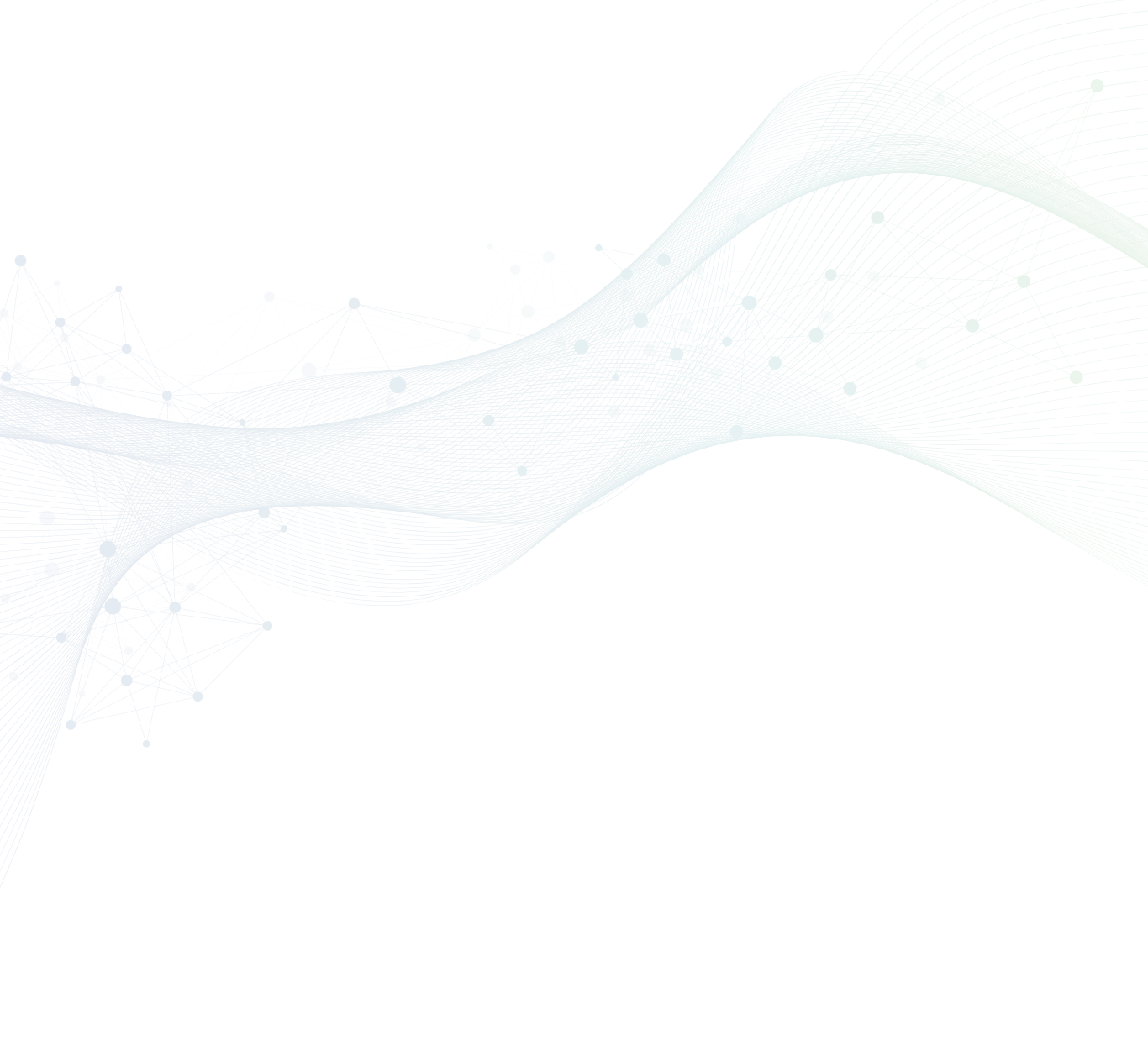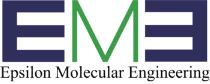哲学と科学の大切さ
世間では哲学などは何の役にも立たないのではないかと思われているのではないかと少々心配している。もっとも哲学とはデカルトやカントやサルトルなどのいわゆる哲学者の思想を学び,書物を読むことだと思われていたらそうかもしれない(先達の思想に学ぶことはそれなりに大切なことは十分承知しているが)。私がここで哲学と述べているのはモノの本質を問いかけ,深く徹底的に思索する姿勢とでもいった方がよいだろうか。
若い頃,特に高校を中退してから何をして生きていけばよいか考えあぐんでいた頃,「人生とは何か」「社会とは何か」等々,答えのない質問しては書物のどこかに答えが書いてあるのだろうと思い,図書館に通っては乱読していた。
今になって思うと、小林秀雄が言うように「書物に傍線を引いて世の中を理解する」ことができるほど、世の中は甘くない。実生活の中で社会的存在として働くなかで徐々にわかってくるものだと思うのだが。
ともあれ同級生たちが少しでも偏差値を上げようと受験勉強に奮闘している時期に、超絶とした態度で哲学書やほとんど受験と関係ない本を乱読するという度胸だけはついたような気がする。(もっともテスト勉強をしなくてはいけない時期になると文学書などを読みたくなるものだが)
さて、このようなある意味、緊迫した状況でも少し距離を置いて考える習性は意外なところで役に立った。
前回のコラムで最初に勤務した高校が世間で言う教育困難校というところで、そこで実際にノイローゼにならずに(実際、ノイローゼになった先生方もいた)5年間過ごすことができたのは、過酷な状況の中で自分自身の問いかけとして「なぜ理科を学校で教える必要があるのか」という命題を考える対象としていわばこの学校を研究対象として考えていたからだった。別な言い方をすれば「科学教育とは何か」という問いだった。(この学校にとって理科よりももっと大切な必要なことがあるのではないかとも思ったりした)
「教育とはこうあるべきだ」という理念先行ではなく、研究対象として観察していると、いろいろやらかしてくれる生徒の行動に腹を立てるよりも、どうしてこのような行動をとるのかを分析的に、時には仮説を立てて理解しようとするようになる。すると不思議なことに生徒たちがすぐに叱らないこの「ヘンな教師」にいろいろと話もしてくれるようになって、私の方も「時には暴れたくもなるわな」と思ったりするのである。
そうこうするうちに私はどんな生徒たちとも人間としての付き合い方ができる自信がついてきて、いつの間にかクラスも落ち着いてきた。
哲学とは「こうあるべき」と説くことではなく、現状をベースにしながらもそこから少し距離をおいて問いかける力ではないかと思う。デカルトは『方法序説』でこれを行い科学の方法を示した。科学の方法に従い「問い」かけていけば、必ず答えを見つけられる。
EMEが「科学的に考える」を社是にする所以である。
(少々わかりづらい話をしてしまいましたが、ご容赦を)