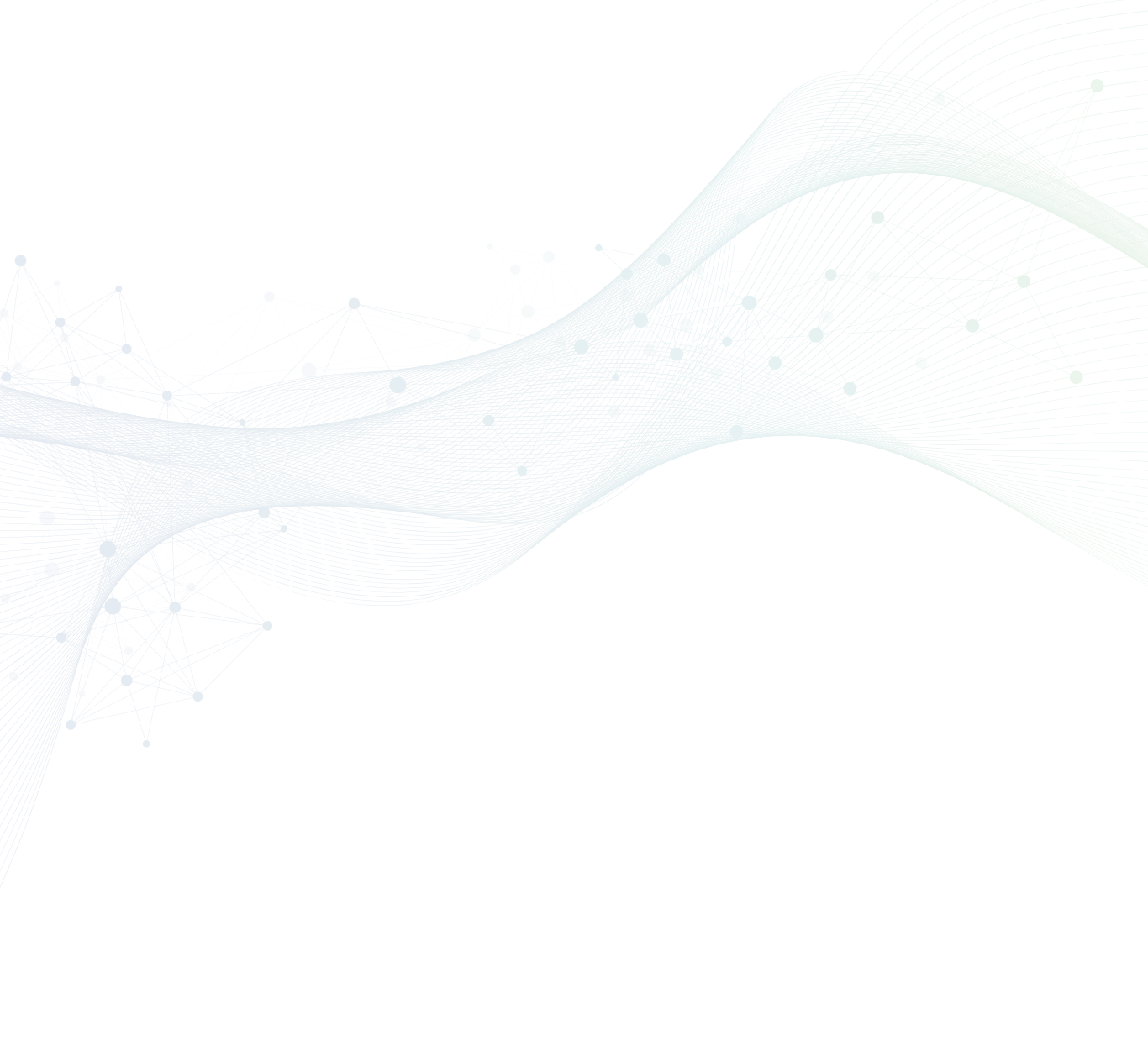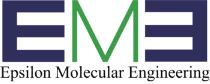今回のコラムは、次世代バイオ医薬のブレークスルーとなるVHH抗体をイントロします。
1993年VHH(Single domain antibody)が報告された。ラクダ科では通常の抗体に加えVHH抗体が末梢血中に存在していた。日本では当時藤田保健衛生大学教授の黒澤良和先生がVHH抗体研究の第一人者として精力的に研究を進めていた。演者は英国MRCより帰国した直後で、研究会でお会いした黒澤先生がラクダ抗体の魅力を力説されていたことを昨日のように思い出す。当時はヒト化抗体の熾烈な開発競争が始まったばかりであり、VHH抗体の素性もまだはっきりしてなかったことから、VHH抗体創薬に取り組んだのはベルギーの研究グループ(後のAblynx社で2018年にSanofi社の傘下に)などごく一部で、大手製薬企業は興味を示さなかった。その後、抗体医薬はますます盛んになり、現在では60品目を超える抗体医薬が上市され、バイオ医薬品の中心として君臨している。もちろん、この間には次世代抗体の候補として様々なタンパク分子からのscaffoldが報告されてきたが、抗体由来の低分子化抗体ScFvがBITEやCAR-Tに応用されるようになったが、抗体医薬に大きなパラダイムシフトを起こすような次世代分子は台頭しなかった。VHH抗体も表舞台に出ることはなかった。従って、2018年に初のVHH抗体医薬品Caplacizumabが承認された時には多くの驚きの声が上がった。現在では30品目以上のVHH抗体が臨床評価段階にある。
それでは、いよいよVHH抗体パラダイムシフトを起こすのか? そこで過去からの研究を改めて調べてみるとVHH抗体は創薬分子して非常に高い潜在性を持つことが判る。多くの方はまず抗原性を疑うが、VHH抗体はヒトVHファミリー3と90%近い相同性を有する。様々な物理化学的性も創薬に適しており、微生物宿主での工業生産も可能になっている。多くの抗体研究者が最も気にするのはその短い半減期だが、臨床においてはすでに血中半減期を抗体医薬並みに持続させる技術も開発され、致命的な問題にはならない。EMEがVHH抗体創薬に最も魅力を感じるのは、VHH抗体はペプチドアプタマーのように機能するCDR3の構造特性にある。つまりVHH抗体の標的分子との結合様式はVL-VHによる従来の抗体とは異なり、標的分子上の結合部位(エピトープ)はVHH抗体が遥かに多様性を有している。つまり従来の抗体では認識できないエピトープが確保でき、新しい創薬の可能性が生まれる。例えば、複数膜貫通タンパクの中には細胞外に露出してる部分が少ないため抗体の取得が難しい場合でも、VHH抗体を用いれが結合するものが幾つも取得でき、創薬が難しいと言われてきた標的分子が扱えるようになった。
今後、数回にわたり、次世代のバイオ・抗体医薬の筆頭候補として踊り出てきたVHH抗体創薬について、そのハイスループットスクリーニングに技術等も含めてグローバルな研究の状況について紹介する。