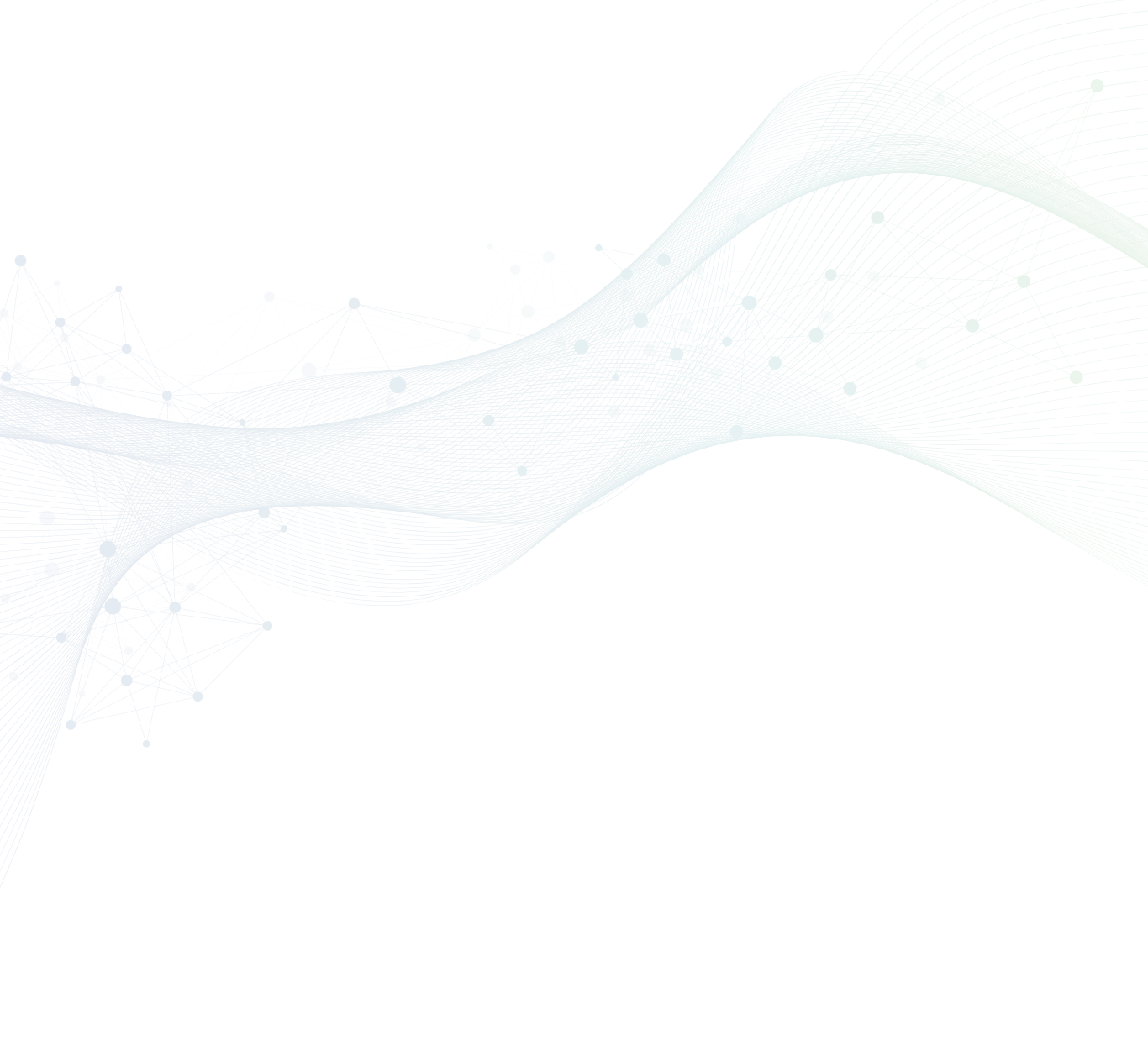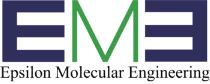cDNA displayのはじまり
cDNA displayの始まりは1997年にFEBS Lettに発表された“in vitro virus”が起点となる。これは当時埼玉大学の伏見先生がin vitro (試験管)で無細胞翻訳系を用いて合成するため、試験管を宿主とするウイルス型分子であるということで“in vitro virus (IVV)”と名付けた。しかし、In vitro virusというネーミングよりはほぼ同時期に発表されたハーバード大学の著名なSzostak博士らのグループが名付けたmRNA displayの方がPhage displayの連想からわかりやすいため良く使われるようになった。しかし、IVVにしてもmRNA displayにしても抗生物質のピューロマイシンがDNAを介してmRNAの3‘末端に付加させたものを無細胞翻訳系で合成するとmRNAにコードされたポリペプチドと共有結合で連結したmRNA-タンパク質連結体ができるということは共通である。ただ、このmRNA displayはどうしてもphage displayに比べ脆弱性があり、これは分子を選択する条件をどうしても制限する。この克服のためにmRNAとポリペプチドを連結した形からcDNAとポリペプチドを連結した形に変換するためのキーとなるのが、EMEが提供するピューロマイシン・リンカーである。(そこでネーミングも“cDNA display”と敢えて替えさせていただいた)
cDNA displayの改良とピューロマイシン・リンカー
mRNAとポリペプチドのピューロマイシンを介した連結効率もPUREシステム(無細胞翻訳系)の改良により60%に達した(VHH抗体の場合)。以前は10%に満たない効率で実はライブラリ調整に多くの無細胞翻訳系を要していた。そもそもmRNAとDNAの連結効率も16時間反応で50%程度しかライゲーションされない効率の悪さだったのだが、北陸先端大の藤本先生のcnvKの利用で今では数分で連結する。このようにあらゆる改良がされて本来の意味で実用的になったcDNA displayであるが、ただ一つ、キーとなるピューロマイシン・リンカーの作製に少し工夫が必要であるためになかなか研究者に拡がりにくいところがあった。これを手に取りやすくすることで、cDNA displayは格段に使いやすくなり、だれもが実験できるようになると考えている。
cDNA displayへの思い
そもそもEME創業の思いは「cDNA displayの社会実装」である。創薬を通じた社会実装もあるが、この方法自体を研究者の方々に利用していただき様々なアイデアと結びつくことで新たな医薬開発等につながれば、ゆくゆくはより良い医療社会に貢献できると信じている。
このコラムのキーワード
cDNA display技術:遺伝子型/表現型対応付けによる目的タンパクの取得を試験管内で行うことができる技術。従来のファージディスプレイを大幅に超える1013-14(10兆~100兆)種類の分子を一度にスクリーニングすることが可能。
cnvKリンカー:当社独自のcnvKリンカーであり、cDNAディスプレイ法において、遺伝子型-表現型対応付けのキーテクノロジーであるピューロマイシンリンカー。特定部位でハイブリダイゼーションしたmRNAとcnvKリンカーにUV照射することで光架橋により迅速に連結し、mRNA-cnvKリンカー複合体が形成される。これにより一連のcDNAディスプレイ分子調製時間の大幅な短縮が可能になった。最近では米国ノースウエスタン大学の坪山幸太郎 博士研究員(現 東京大学生産技術研究所講師)、Gabriel Rocklin助教らの研究チームが、当社のcnvKリンカーを用いて、独自開発したcDNAディスプレイタンパク質分解法を用いた最大90万種類のタンパク質ドメインのフォールディング安定性を超並列かつ高速に(1週間程度)測定した研究開発成果をNature誌にて発表された。(関連記事はこちら)
VHH抗体:ラクダ科動物の持つH鎖のみで構成される抗体(一本鎖重鎖抗体)の可変領域(ドメイン)のことで、Variable domain of heavy chain of heavy chain antibodyという。通常の抗体と比較して安定性や修飾性に優れている。